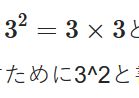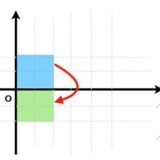どうも、木村(@kimu3_slime)です。
大学の数学科では、およそ3年次の専門科目として、測度論(measure theory)やルベーグ積分(Lebesgue integral)の授業があります。
ルベーグ積分は、概ねリーマン積分(高校までで習う普通の積分)の拡張と捉えてよいものです。例えば、確率論の基礎に応用されます。また、リーマン積分の枠組みでは少し複雑になってしまう収束定理が、よりシンプルな仮定で成り立ちます(優収束定理など)。このへんの話は、ルベーグ積分の教科書にも書かれているものです。
しかし、ルベーグ積分をなぜ学ぶ必要があるのか、これだけではまだ一般論すぎて、学び始めの僕には漠然しているように見えました。「積分を一般化したから何?、極限の順序交換しやすいから何?」と。
今回は、偏微分方程式への応用の観点から、なぜルベーグ積分が必要なのか、どう役立つのかを僕なりに考えてみたいと思います。
偏微分方程式の解を一般的に求めるために
結論から言うと、偏微分方程式の解を一般的に見つけるのは難しく、その解の構成のために、解の候補となる関数の範囲を都合よく広げられるからです。
(もちろんルベーグ積分の使い方は多様でこれだけではないのですが、今回は解の構成にフォーカスして話します)
有名な偏微分方程式としては、ラプラス方程式・ポアソン方程式、熱方程式(拡散方程式)、波動方程式などがあります。
\[ \begin{aligned}\Delta u = 0\end{aligned} \]
\[ \begin{aligned}\Delta u = f\end{aligned} \]
\[ \begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial t} – \Delta u = 0\end{aligned} \]
\[ \begin{aligned}\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} – \Delta u = 0\end{aligned} \]
これらの方程式は比較的シンプルで、解を明示的に得る方法が知られています。例えば、(1次元、有界領域における)熱方程式なら
\[ \begin{aligned}u(x,t)= \sum _{n=1} ^\infty c_n e^{-n^2 \pi^2 t} \sin n\pi x\end{aligned} \]
です。
参考:熱方程式の解き方:変数分離法、フーリエ級数展開(1次元、有界領域)、熱方程式の解き方:フーリエ変換(全空間、N次元)
すべての現象がこれらの方程式で表されるわけではありません。方程式が例えば次のように変化したらどうなるのでしょうか。
\[ \begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial t} – \Delta u = e^{-x^2}u\end{aligned} \]
個別の偏微分方程式を解くために、個別の解法を用いていたら大変です。そもそも、一般の微分方程式において、解がきちんと存在するかどうかもわからないのです。簡単な常微分方程式であっても、解が有限時間で発散するような例もあります。
関数解析を使って調べる
偏微分方程式の解が一意に存在することを保証することを、一般的に調べる方法はないのでしょうか?
例えば行列を使った方程式\(Ax=b\)なら、\(A\)が正則ならその解は一意に存在し、\(x= A^{-1}b\)と表せます。
これを偏微分方程式にも当てはめようとしてみましょう。
偏微分方程式\(-\Delta u = f\)において、行列に対応するものを\(L=-\Delta \)と置き、\(u = L^{-1} f\)と表すことができないか?
ここで、行列(線形代数)では有限次元のベクトル\(x\in \mathbb{R}^n\)を考えていましたが、対応するものは関数\(u\)です。行列に対応する\(L\)はある関数を別の関数に対応させるもので、作用素(operator)と呼ばれます。
じつは、関数\(u\)が生息する線形空間(関数空間)は、一般に無限次元となります。このような問題を考える分野が、関数解析(functional analysis)です。そして、ルベーグ積分は関数解析と非常に相性が良いのです。
関数空間の例として有名なのは、連続関数のなす空間\(C=C^0\)や、微分可能かつ導関数がなめらかな関数のなす空間\(C^1\)などでしょう。
しかし、微分方程式の解を一般的に求めるための空間としては、これらの空間の性質は必ずしも良くないのです。積分を使った\(p\)ノルムを考えると、連続関数列の極限は連続ではなくなってしまうことがあります。
\[ \begin{aligned}\| f\|_p := (\int |f(x)|^p dx)^{\frac{1}{p}},\quad p\geq 1\end{aligned} \]
そもそも、不連続な関数を含めてしまったほうが、関数空間としては収まりが良くなります。それが、例えばルベーグ\(p\)乗積分可能な関数のなす空間\(L^p\)や、その部分空間であるソボレフ空間\(W^{k,p},H^k\)です。
\(C(\Omega)\)で関数列の極限を取ると外側に出てしまうことがありますが、\(L^p\)ではそのようなことがありません。この違いは、\(C(\Omega)\)は完備でなく、\(L^p\)は完備であると呼びます。
空間に完備性があると、関数解析の一般的なアプローチが適用できます。
そのために、微分方程式の「解」という概念を、連続関数でないものに使えるように一般化します。微分方程式と言いながら、(強い意味で)微分できない関数すら解の候補に入れてしまうのです。
仮に\( u\)を微分可能な関数とすると、(境界で0となる)任意のなめらかな関数\(\varphi \)に対して
\[ \begin{aligned}\int _a ^b u \varphi’ dx = -\int_a ^b u’ \varphi dx\end{aligned} \]
が成り立ちます(部分積分)。テスト関数\(\varphi \)は、\(u\)の微分可能性を「引き受けて」います。一旦\(u\)の微分可能性の条件を忘れても、この式自体はルベーグ積分可能な関数で意味を持ちます。つまり、
\[ \begin{aligned}\int _a ^b u \varphi’ dx = -\int_a ^b v \varphi dx\end{aligned} \]
この等式が成り立つようなルベーグ積分可能な関数\(v\)を、\(u\)の弱微分(weak derivative)と呼ぶのです。微分可能な関数は弱微分可能ですが、逆は一般には成り立ちません。例えば、一点で不連続で他の場所で微分可能な関数は、弱微分可能ですが微分可能ではありません。
同様にして、偏微分方程式を連続でない関数にも適用可能な弱形式(weak form)に再定義できて、その解を弱解(weak solution)と呼びます。こういう枠組みにすれば、解の候補となる関数のなす空間が完備となり、関数解析の手法が使えるのです。
例えば、(リースの表現定理の一般化である)ラックス-ミルグラムの定理(Lax-Milgram Theorem)と呼ばれるもので、(楕円形方程式の)弱解の存在と一意性が言えます。
また、(放物型、双曲型方程式では)ガラーキン法(Galerkin method)と呼ばれる方法で、基底関数を使った近似解によって真の解を捉えられます。この方法は、偏微分方程式の数値計算、有限要素法の基礎ともなっています。
参考:リースの表現定理とラックス・ミルグラムの定理 – 小澤 徹、数値解析の基礎 – 名古屋大学
微分可能でないかもしれない解(弱解)をつかまえてきて、どんな意味があるのか、という疑問もあるかもしれません。しかし、実際にはこれらの方程式では、解が(強い意味で)微分可能であることを示すことができます。
一旦、広い範囲で解を探してから、その性質をよく調べてみるとなめらかなものだった、と。なめらかさを調べることは、レギュラリティ(regulality)問題と呼ばれます。
まとめ
偏微分方程式への応用の観点から、ルベーグ積分の意義について考えてきました。
偏微分方程式を解くための一般論を調べたい。そのときに、具体的な解の形を得るのは難しいですが、(線形代数でやっていたようなことを一般化した)関数解析的アプローチなら可能です。
しかし関数解析的アプローチの適用には条件があり、それは関数のなす空間が完備であることです。そのためには、連続関数、微分可能な関数、リーマン積分可能な関数のなす空間では不十分で、ルベーグ積分が必要となってくるのです。関数列の(積分的な)極限を取ったときにお行儀が良い、それくらい適切な範囲の関数をルベーグ積分では扱えます。
実際には、微分をより弱い形式、弱微分といった概念を導入して捉えるすることで、偏微分方程式の解を関数解析によって捕まえられます。
ルベーグ積分の導入ということで書き始めた記事でしたが、関数解析のモチベーションにもなる話でしたね。
少し飛ばし気味で難しかったかもしれませんが、ルベーグ積分をなぜ学ぶのかという疑問に、偏微分方程式的な立場から答えられていたら嬉しいです。
木村すらいむ(@kimu3_slime)でした。ではでは。
Partial Differential Equations (Graduate Studies in Mathematics)
Amer Mathematical Society
売り上げランキング: 33,117