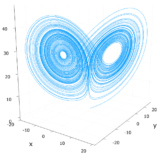どうも、木村(@kimu3_slime)です。
今回は、弱微分の一意性の証明を、変分法の基本補題を利用して紹介します。
弱微分の定義
\(\Omega \subset \mathbb{R}^N\)を開集合、\(u, v \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)\)を局所可積分な関数、\(\alpha \)を多重指数とします。
\(u\)の\(\alpha\)階弱微分が\(v\)である \(D^{\alpha}v =u\)とは、すべてのテスト関数\(\phi \in C_c ^\infty (\Omega)\)に対し、
\[\int_{\Omega} u (D^{\alpha}\phi) dx=(-1)^{|\alpha|}\int_{\Omega} v \phi dx\]
一意性の証明
\(u\)の弱微分の(ほとんど至る所での)一意性を示すためには、 \(D^{\alpha}v =u\)、 \(D^{\alpha}w =u\)を満たすような\(v,w\)が存在するならば、\(v =w \,(\mathrm{a.e.})\)でなければならないことを示せば良いです。
仮定 \(D^{\alpha}v =u\)、 \(D^{\alpha}w =u\)より、すべての\(\phi \in C_c ^\infty (\Omega)\)に対し、
\[\int_{\Omega} u (D^{\alpha}\phi) dx\\=(-1)^{|\alpha|}\int_{\Omega} v \phi dx \\=(-1)^{|\alpha|}\int_{\Omega} w \phi dx\]
が成り立ちます。後半2つの等式から、\((-1)^{|\alpha|}\)をキャンセルし、積分の線形性を用いれば、
\[\int_{\Omega} (v-w) \phi dx =0\]
です。
ここで一般的な性質として
変分法の基本補題(fundamental lemma of caluculus of variations)
\(\Omega \subset \mathbb{R}^N\)を開集合、\(f \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)\)とする。
すべての\(\phi \in C_c ^\infty (\Omega)\)に対し、
\[\int_{\Omega} f \phi dx =0\]
ならば、\(f=0 \,(\mathrm{a.e.})\)
を用いましょう。証明はたとえば黒田「関数解析」を参照。どんなテスト関数との積を考えても積分が0になるならば、そのような関数はほとんど至る所0でしかありえない、という主張です。
\(f(x)=v(x)-w(x)\)と置けば、\(L^1_{\mathrm{loc}}\)は線形空間なので、\(f \in L^1_{\mathrm{loc}}\)です。そしてすべての\(\phi \in C_c ^\infty (\Omega)\)に対し、
\[\int_{\Omega} (v-w) \phi dx =0\]
が成り立っています。よって、変分法の基本補題により、\(f=0 \,(\mathrm{a.e.})\)、すなわち\(v=w \,(\mathrm{a.e.})\)が言えました。
どんな関数\(u\)を考えても、\(v,w\)がその弱微分であるならば、両者はほとんど至る所で一致します。これが弱微分の一意性です。
以上、弱微分の一意性の証明を、変分法の基本補題を利用して紹介してきました。
弱微分という考え方が一意に定まる前提として、ほとんど至る所というルベーグ積分の考え方が有効なのがわかりますね。
木村すらいむ(@kimu3_slime)でした。ではでは。
Evans, Lawrence C.(著)
¥16,299 (2022-08-19時点)
こちらもおすすめ
ソボレフ空間W^{k,p},H^kとは:多重指数、ノルム、内積
連続関数、可積分関数の線形空間(関数空間)、微分と積分の線形性とは