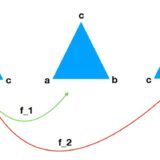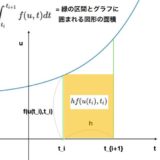どうも、木村(@kimu3_slime)です。
「一般の五次(以上)の代数方程式には、(代数的な)解の公式が存在しない」理由を群や体の概念を通して説明するガロア理論は、抽象代数学の教科書のひとつの到達点とされたり、一般の解説書が多く出ていたりと、学んでみたい方が多いのではないでしょうか。
しかし、いざ数学の代数学の教科書を開いてみると、ガロア理論にたどり着くまでの道のりは果てしなく長いです。しかも、概念が結構込み入っています。
今回は、群論の基礎知識だけをベースに、ガロア理論のポイントを簡単にまとめてみようと思います。
群論の予備知識としてはこの辺をどうぞ:群論入門~回転群と巡回群を例に、群の定義・同型・位数を解説、対称群の基礎:置換・互換の記法、符号、交代群を解説
ガロア理論以前に知られていたこと
最初に知っておきたい、もとい間違えないでおきたい、ガロア理論以前に知られていた事実を紹介します。
高校では、2次方程式の解の公式を学びます。解の公式とは何かというと、方程式の係数の加減乗除とべき乗根の有限回の組み合わせによって解を表す式のことです。
例えば、2次方程式\(ax^2+bx+c=0\)の解は
\[ \begin{aligned}x_1,x_2 = \frac{-b\pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}\end{aligned} \]
で、確かに係数を引いたり掛けたり割ったりルートを取ったりしたものになっています。
3次方程式にはカルダノの公式、4次方程式にはフェラーリの公式と呼ばれる公式が存在することが、1545年にはカルダノによって既に知られていました。(ちなみに、4次方程式の解の公式はかなり長い式になります)
また、五次方程式には解が存在しないわけではありません。必ず存在します。\(n\)次の(複素係数で一変数の)多項式には、複素数の範囲で(重複度込みで)\(n\)個の解が存在します。これは代数学の基本定理と呼ばれ、1799年にガウスによって示されたと言われています。虚数解、複素数解をもちろん含めての解の公式です。
さらに、「五次以上の代数方程式には解の公式が存在しない」ことを最初に示したのは、ガロアではありません。その事実自体は、アーベル=ルフィニの定理として、1824年頃にアーベルが示したとされています。
ガロアは、その事実(アーベル=ルフィニの定理)をよりわかりやすく、一般的に発展可能な形で示したことが大きな功績と言えるでしょう。
また、アーベル、ルフィニ、ガロアの非可解性の証明において解の置換を考えるというアイデアは、ラグランジュによる部分があります。ラグランジュは、2次・3次・4次方程式の解を得る統一的な方法を通して1770年には置換を見出していました。
参考:Galois’ predecessors – The Development of Galois Theory, Fiona Brunk
ちなみに、アーベル=ルフィニの定理は、「一般の」方程式に解の公式が存在しないことを述べています。つまり、特殊なケースでは代数的な解の表示が得られます。例えば、\(x^5-1=(x-1)(x^4+x^3+x^2+x)\)なので、四次方程式が代数的に解けることからこれも代数的に解けます。また、\(x^{17}-1=0\)が代数的に解けることは、ガウスによって知られました(正17角形の作図可能性)。
また、代数的な解の公式が存在しないと主張するのみであり、代数的でない解の表示式はあり得ます。「無限回の」加減乗除、すなわち解の近似列を構成することもできます。コンピュータで代数方程式の解を求める方法として、ニュートン法や連立法が知られています。
2次方程式にはなぜ解の公式がある?
簡単な例を通して、ガロア理論の発想に近づくことを試みます。
高校では、2次方程式\(f(x)=ax^2+bx+c=0\)の解の公式は、因数分解、いわゆる「平方完成」によって導きました。
しかし、これではより一般の方程式に対し、「なぜこんな表示が得られるのか」がわかりません。一般の方程式では、解の公式があったとして、それがどんな形で表されるか予想できません。どのように因数分解すればいいかわかっているなら、苦労しないのです。
では、ラグランジュの方法を紹介しましょう。
どんな解かわからなくても、解自体は確実に存在します。そこで、今回は2つの解を、未知の数として\(x_1,x_2\)と置きましょう。このとき、
\[ \begin{aligned}ax^2 +bx+c= a (x-x_1)(x-x_2)\end{aligned} \]
となります。この未知数に関しては、解と係数の関係から
\[ \begin{aligned}x_1 +x_2=-\frac{b}{a},x_1 x_2=\frac{c}{a}\end{aligned} \]
が成立しています。なんとかして、\(x_1,x_2\)を\(a,b,c\)で表せないでしょうか。
ここで、\(x_1+x_2,x_1x_2\)を変数\(x_1,x_2\)の基本対称式と呼びます。一般に、変数を交換しても値の変わらない式を対称式と呼びます。
そして、すべての対称式は、基本対称式の四則演算によって表せることが知られています(対称式の基本定理)。
つまり、解\(x_1,x_2\)を何らかの対称式として表せれば、それは基本対称式に分解でき、それは既知の値(係数)で表せるわけです。
解を2つの部分、対称式\(R_1\)とそうでない部分\(R_2\)に分けてみましょう。
\[ \begin{aligned}x_1= \frac{1}{2}(R_1+R_2),x_2 =\frac{1}{2}(R_1-R_2)\end{aligned} \]
\[ \begin{aligned}R_1 = x_1+x_2,R_2=x_1 -x_2\end{aligned} \]
\(R_1,R_2\)はラグランジュの分解式、ラグランジュ・レゾルベント(Lagrange resolvent)と呼ばれます。\(R_1,R_2\)が求まれば、解が求まるわけです。
\(R_1\)は対称式ですが、\(R_2\)は対称式ではありません(符号が変わる)。しかし、\(R_2\)から対称式を作り出すことはできます。
\[\begin{aligned} R_2^ 2& = (x_1-x_2)^2\\&= (x_1 +x_2)^2 -4x_1 x_2 \\ &= \frac{b^2}{a^2} – \frac{4c}{a} \end{aligned}\]
と、対称式になったので、基本対称式の加減乗除に分解でき、値を求めることができました。したがって、平方根を取れば
\[ \begin{aligned}R_2 = \frac{\sqrt{b^2 -4ac}}{a} \end{aligned} \]
となります(つまり、\(R_2\)は判別式の部分に対応しています)。よって、解は求まって
\[ \begin{aligned}x_1 ,x_2 =-\frac{b}{2a} \pm \frac{\sqrt{b^2 -4ac}}{2a}\end{aligned} \]
と得られました。
ラグランジュの方法は、何を行っているのでしょうか?
\(n\)次の方程式において、解は未知ですが\(x_1,\dots,x_n\)と表せます。解と係数の関係によって、\(x_1,\dots,x_n\)の基本対称式が係数の加減乗除として得られます。そして、解をラグランジュ・レゾルベント\(R_1,\dots,R_n\)に分解します。
一般にラグランジュ・レゾルベントは対称式とは限りませんが、もしそこから対称式が得られたなら、それは基本対称式によって表わせます。すなわち、解が得られるわけです。
これを解の置換という立場から眺めてみましょう。
\(x_1+x_2,x_1 x_2\)のような基本対称式は、あらゆる置換によって不変です。方程式の係数は、常に解の基本対称式なので、解を入れ替えても値が変わりません。
一方で、解そのもの\(x_1,\dots,x_n\)、あるいはラグランジュ・リゾルベント\(R_1,\dots,R_n\)は、当然解の入れ替えについて対称ではありません。つまり、単位置換\(e\)のみによって不変です。
例えば、\(\phi(x_1)=x_2,\phi(x_2)=x_1\)という置換を考えると、\(L_2\neq \phi(L_2)\)でした。しかし、\(L_2 ^2 =\phi(L_2^2)\)なので、\(L_2^2 \)は求められました。\(L_2^2\)は\(S_2\)において不変です。
つまり、解の公式を得ることはこう言えます。任意の置換のなす群\(S_n\)について不変な数は、係数として求まっています。\(S_n\)を適切に小さくして、解に対応する自明な群\(\{e\}\)を得られるならば、解は得られて、そうでなければ解は得られない、と。
こうした流れで、解の公式と(対称)群は結びついています。
少し先の言葉で、詳しく解説せずに話を書いておきます。
数体\(K\)(\(\mathbb{Q},\mathbb{R},\mathbb{C}\)など)上の多項式\(f\in K[x]\)は、\(K\)を適切に拡大した体:分解体\(E=K(x_1,\dots,x_n)\)を考えることで、一次式の積に分解されます。例えば、\(x^2+1\)の分解体は\(\mathbb{R}(i):=\{a+bi \in \mathbb{C}\mid a,b \in \mathbb{R}\}\simeq \mathbb{C}\)で、\(ax^2+bx+c\)の分解体は\(\mathbb{Q}(\sqrt{b^2 – 4ac} ):=\{p+q \sqrt{b^2 – 4ac}\in \mathbb{C} \mid p,q\in \mathbb{Q}\}\)です。
もし\(K\)に冪根を付加していくことで分解体が得られたら、多項式は冪根によって解けるということ。すなわち、冪根によって解けるとは、冪根による拡大と呼ばれる拡大体の列で、分解体を含むようなものを得ることと言い換えられるわけです。
このような拡大体の列が得られるかどうかは、ガロア理論の基本定理により、多項式のガロア群が可解かどうかに対応します。
ガロア群とは、\(E\)の\(K\)上の自己同型のなす群\(G_{E/K}\)、つまり解の入れ替えをする写像の集まりです。2次方程式では、\(\phi\in G_{E/K}\simeq S_2\)でした。(ガロア)群が可解であるとは、自明群へ減少していく正規部分群の列で、隣り合う部分群の商群\(G_{i-1}/G_i\)が単純かつ巡回群となるものが存在することです。
2次方程式ならば\({e}\subset S_2\)でガロア群は可解。\(L_2^ 2\)を考えることで解けたことは、\(S_2/{e}\simeq S_2\simeq C_2\)が巡回群であることに対応しています。3次方程式ならば、\({e}\subset A_3 \subset S_3\)となり、ガロア群は可解です。
こうして方程式の可解性(体の冪根による分解体への拡大)は、それに対応するガロア群(解の入れ替えのなす群)の可解性、すなわち対称群はどんな正規部分群の列を持つか、という問題へ落とし込まれます。5次方程式が解けないことは、\(S_5\)の正規部分群を考えたときに「何か」が起こることに対応するわけです。
ガロア理論の論理構成
方程式の可解性と群論・体論の結びつきを、少しは感じていただけたでしょうか。
ここからは、松坂「代数系入門」をもとに、ガロア理論の論理構成を要約してみます。用語の定義や詳細な記述は省略します。
示したいのは、次のことです。
定理23:アーベル=ルフィニの定理
\(K\)を標数0の体とする。\(n\geq 5 \)のとき、\(K\)上の\(n\)次の一般多項式は、冪根によって解けない。
これは主に次の定理から示されます。
定理22
多項式\(f\)が冪根によって解けるならば、\(f\)の\(K\)上のガロア群は可解である。
(対偶:ガロア群が可解でないならば、多項式は冪根によって解けない)
(これは逆も成立します)
これはガロア理論の主結果で、肝となるガロア理論の基本定理(定理13)から導かれます。ざっくり言えば、「体の拡大は、群の分解に対応する」という定理です。方程式の可解性という体の性質(調べにくいこと)が、群の可解性(調べやすいこと)に置き換えられます。
この定理によって、一般多項式のガロア群(と呼ばれる群)が可解(という性質)を持たないことを示せば十分となりました。
一般多項式のガロア群はどのようなものか、そして可解かどうか。それは次の2つの定理から示されます。
定理13
一般多項式のガロア群\(G_{E/K}\)は、\(S_n\)に同型。
定理18
\(n\geq 5\)ならば、\(S_n\)は可解でない。
以上をまとめると
- 定理22:多項式\(f\)から定まるガロア群が可解でないならば、\(f\)は冪根によって解けない
- 定理13:一般多項式のガロア群は\(S_n\)
- 定理18:\(n\geq 5\)ならば、\(S_n\)は可解でない。
- よって:\(n\geq 5\)ならば、一般多項式\(f\)は冪根によって解けない
という流れになっています。
現時点の謎としては、「可解って何?」「多項式の可解性が、なぜ群と対応するの?」が残されています。
ここで挙げたような定理を目標にすれば、ガロア理論も少しはきちんとフォローしやすいのではないでしょうか。
木村すらいむ(@kimu3_slime)でした。ではでは。
こちらもおすすめ
図形の対称性を記述する二面体群、多面体群、点群・結晶群について解説
群論・ガロア理論の一歩手前から学ぶ 「アーベルの証明」レビュー